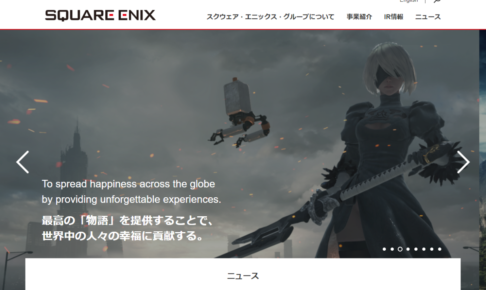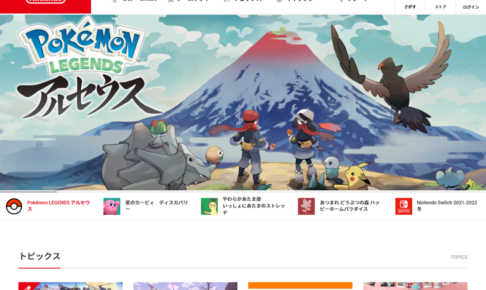インディーの小規模開発会社であるトイディアがリリースしたRPG『ドラゴンファング』。「ローグライク」と呼ばれるジャンルのこの作品が、なんと100万ダウンロードを突破した、という報には、驚かされた人もいるのではないだろうか。
この『ドラゴンファング』が大きく羽ばたいた理由について、トイディアの松田崇志社長にインタビュー。ハードメーカーから自分の会社を立ち上げ、アプリを100万ダウンロードにまで導いた秘訣とは?
前編となる今回は、セガ、マイクロソフトと、家庭用ゲームのハードウェアメーカーを渡り歩き、インディーでゲームアプリを作る会社を立ち上げるまでの経緯を伺った。松田さんはどうして、あえて自分でやることを目指したのか!?


松田崇志
株式会社トイディア
代表取締役 CEO
『ドラゴンファング』プロデューサー
(敬称略)
◆それはセガから始まった
――トイディアで作られた『ドラゴンファング』が100万ダウンロードを達成したということで、おめでとうございます。
松田 ありがとうございます。先日開催の「Unite 2015 Tokyo」に登壇させていただいて、その時点で120万を超えたとお話させていただきました。いまは125万ダウンロードくらいですね。
――これがどれだけ驚くべきことかを知るには、トイディアがどういった会社かを知る必要があると思うので、自己紹介を含め、お伝えいただけますか。
松田 もともと私は、大学を卒業して、セガに入りました。当時はまだドリームキャストを作っていて、ハードウェアメーカーとして活きが良かった時代です。もともとセガは、既存のタイトルにない、冒険心にあふれたタイトルが多かったと思うんですね。
――セガらしい、という雰囲気ですね(笑)。
松田 ビビッドな色使いが多かったり、ゲーム内容も斬新だったり、ですね。僕は多摩美(多摩美術大学)の出身なんですが、ものづくりを勉強し、ビジネスについて本を読んで、模倣でないモデル作りがいかに表現にとって大事かを学びました。どうせアートをやるならということで、ゲーマーである自分にはセガがとても魅力的だったんです。ゲームとしては、投げっぱなしなところもあるんですけれど(笑)。
――逆にそこがマニア心をくすぐるところでもありますね(笑)。
松田 そうして紆余曲折あってセガに入れていただきました。当時はアーケードゲームこそが表現の最高手段でしたので、一番チャレンジャブルでエキサイティングな場所として、『バーチャファイター4』を作っていたセガのAM2研(編注:第2ソフトウェア研究開発部)の門を叩かせていただき、採用していただけました。
――『アウトラン』『スペースハリアー』『アフターバーナー』『バーチャファイター』などアーケードゲームの傑作を生んだ、伝説的な部署ですね。
松田 そうして元気が良かったセガで、まず国内でのゲームの作り方、とくにコンシューマ(家庭用)のゲームを学びました。セガでは同期が300人ほどいまして、その一部がいまのトイディアのコアメンバーにもなっています。現在の副代表の澤田は、ソニックチーム(編注:『ソニック』シリーズなどを生んだチーム)でプログラミングをしていました。
――AM2研とソニックチームの若手が仲が良いというのも、なかなか面白いですね。
松田 私が入ったのが1999年で、すごく同期の仲が良かったんですよ。コンシューマもアーケードも全然関係なく、定期的に飲み会をしていたんです。そこで、部署関係なく、横の情報のつながりの大事さを感じたりもしました。セガの社内文化では、それぞれの作り方に高いプライドを持って技術を秘匿する傾向が強かったんですが、飲み会で集まって言える範囲で情報交換すると、作り方にも多くの選択肢があることが分かったんです。
AM2研は技術力もあって素晴らしいクリエイターが数多くいましたので、ペーペーとしてAM2研流の作り方を教えていただきつつ、グローバルなものの作り方を考えないと淀む可能性がある、という視野も持つことができました。

◆マイクロソフトで知ってしまったこと
――ラッキーな環境だったかもしれませんね。
松田 そうして何年か過ごしていった後に、マイクロソフトがXbox Japan Studioを作るにあたって、ヘッドハントをしてくださったんです。私は当時、2Dも3Dも両方やれたので、初期の創立メンバーとしてお声がけいただきました。
――Xboxの初期も初期、ファーストメンバーなんですね。
松田 厳密には自分より前にもいらっしゃいますが、ほぼファーストメンバーですね。そこからXbox Japan Studioが終わる最後までいましたので、マイクロソフトでのキャリアが、ゲーム人生の中で一番長いキャリアということになります。Xboxが全然売れなくて、Xbox 360になっても全然売れなくて、アメリカ本社とやりとりして、タイトルも作っては砕かれを繰り返し、4本あったラインが2本になり、リストラ騒ぎもあり……いろいろでした。
マイクロソフトで最後に関わらせていただいたタイトルが、坂口博信さんが製作総指揮をされた『ロストオデッセイ』というRPGです(編注:音楽に植松伸夫氏、キャラクターデザインに井上雄彦氏、一部シナリオに重松清氏など豪華な布陣で制作された)。当時のコンシューマでは先進的だったアンリアルエンジンを用いて、Xbox 360のハードウェアで最高級のグラフィックを示して是非を問う、というタイトルでした。ただ、正直言ってあまり売れませんでしたね。
――ソフトウェア側の販売数は、どうしてもハードウェアの普及で決まってしまいますものね。
松田 そこがすごく重要で、ドリームキャスト時代も「ドリームキャストかPS2か」、Xbox 360でも「Xbox 360かPS3か」と、ハードウェアがありきで、ソフトを作っている我々はそれに左右されてしまうんです。私のビジネスは、サラリーマンとしては「ゲームをどう面白く完成させるか」でしたが、ハードウェアの売れ行き次第で、最高に売れても何人まで届くか、作っている途中でもう分かってしまうんですよ。
――悲しいかな、天井が見えてしまう。
松田 ゲームの開発がこれから山場を迎えるときに、どうやらドリームキャストは自分のタイトルが出るまでに15万台程度で、一方PS2は「やったぜ100万台」と言っているとなると、チームの気持ちがシュンとしてしまうんですよ。日本人の良さはそれでも手を抜かずに素晴らしいゲームを作り上げることなんですけれど、ハードウェアありきで勝負が決まってしまうと、どこかで作り手の情熱を取りこぼしてしまう。それでは続けられないな、と思う気持ちがあったんです。ゲームそのものをユーザーに届けるためには、プラットフォームビジネスには限界を感じたし、自分には合わないと思うようになったんです。

◆スマートフォンに魅入られた理由
――ハードの母数の問題は、コンシューマでは避けて通れませんからね。
松田 それと、マイクロソフトで海外のクリエイターとも付き合えた中で、とある外国人アーティストに「日本の『パックマン』『Mega Man(ロックマン)』に憧れてゲームクリエイターになったが、いまのXbox Japanは覇気もないしクリエイティビティもない。ゼロから何かを生み出す魔法使いの雰囲気がない」と言われたんです。ものすごく愛情があって、わざわざ日本にまで来てくれたのに、日本のクリエイターのサラリーマン化しすぎた現状に失望して帰っていった。
それには私自身も悔しかったんです。本当にゲームを作りたいなら、覚悟してインディーズに行ってでも勝負しないと、「ゲームが大好き」が嘘になると思ったんですよ。海外ではもうインディーズが盛り上がっていて、自信がある人は企業を辞めて、自分たちなりのパッケージングでゲームを作り、エゴをぶつけあっていました。一方、日本はサラリーマン化して、転職でも給料の安定が第一。一度国境が外れたら、そんなクリエイターはもう使い物にならないな、と思ったんです。
――売れるタイトルにアサインされるかどうかで転職を決める、という話も聞きますね。
松田 チャンスや可能性があるタイトルをそういう人に任せて、劇的にジャンプアップするかというと、たぶんならないんです。そして、ハードウェアがコンシューマからインターネットに接続されたPCに移り、PCからいまのスマートフォンになった時代に、そういう流れが出てくるのは、早いうちからなんとなく分かっていたんですね。そうなったときに、勝負できないクリエイターに慣らされてしまうことが、すごく怖かったんです。
――マイクロソフトにいたからこそ、分かる空気感もあるかもしれませんね。
松田 それじゃダメだな、と思っていたときに、友達の勧めでiPhone4を触る機会がありました。私は頭が固くてずっとガラケーを使っていたんですが、「松田が言ってたのはこういうことなんじゃないか?」ということで見せてくれたんです。私は、ユーザーにゲームを最初から最後まで、何なら同人でもいいから届けるパッケージングをする、ということを考えていたんですが、iPhoneがあれば、もうそれが企業にいなくてもできるじゃないかと。確かにAppStoreには、すでに海外のゲームがフリーミアムで、高いクオリティで、いろいろな形で溢れていた。かつ電話として常に持ち歩くものでもある。これは最高だな、と思ったんです。
――スマートフォンへの大きな転機ですね。
松田 Appleに登録するのに30%ロイヤリティが必要だけれど、残り70%が自分の手元に来るなら、これは仕事にできる、と思ったんです。もしゲームメーカーでゲームを作りたいと思ったら、まず会社で上の立場になって、プレスはここで、マニュアルはいつで、さらに流通ありきで……という制約の中で考えなければいけなかったところを、自分、Apple、ユーザーの三者で済んでしまう。それがこのクオリティでできるんだ、というところに痺れました。
時代としてはまだ独立してまで始める人はいませんでしたが、自分はあまり学習速度が早いほうではないと思っていたので、いま気づいたならいまやらないといけないと思ったんです。後になって大手がドワーっと参入した後では、その中のどこかに入れてください、と言うしかなくなってしまうので。
――確かに、先行者の強みはありますからね。
松田 自分自身にビジネスの商才があるとは思っていませんでしたけれど、クリエイターとしてゲームを一生続けていきたい気持ちだけは変わりませんでしたし、他のビジネスで面白い人生も思い描けなかった。iPhone4という夢のハードに出会った段階で、いま自分はこれだ、と思ったので、昔から声をかけていたメンバーに、いよいよ独立しようと思うので一緒に夢を見てくれないか、と声をかけました。
これが、トイディアというインディーズのゲーム会社を作ったいきさつになります。

◆クリエイターの最小単位は何人か?
――なるほど。とはいえ、ハードメーカーを渡られて、次にいきなりご自身でインディーズメーカーを始めるのは、やはり冒険ではありますね。
松田 独立にはお金の面などのリスクはありますが、自分のゲームを作りたいのなら、もう大きなハードウェアメーカーにしがみついていてもダメな時代になっています。なぜなら、売れなくなってきているし、クリエイターの意見が会社内でも全然通らなくなっていますから。大きな会社にはメリットもありますが、作り方も決まってしまっているので、よほどの立場、実績、タイトルがない限り、自分の好きな作り方はほぼ許容されません。マイクロソフトで何して来たか知らんけど、ここでは丁稚からだよ、というのが見えていますから。
――良くても、いちディレクターからかもしれませんね。
松田 マイクロソフトでも、大きく恵まれたタイトルに私自身が貢献できた気持ちもなかったし、世間的に通りが良い実績もありませんでした。クリエイターとしては、やりきれていない自分を感じていたんです。でも、やはりゲームしかなかった。好きで好きで、もっと作りたいものもありました。インディーズで早々に船出をすることだけが、自分自身の可能性を信じられる選択肢だったので、あまり悩みはなかったですね。
――そうして始めたトイディアは、最初は何人からのスタートですか?
松田 ふたりです。私と、先ほど言った澤田です。トイディアで最初に考えたのは、ゲームクリエイターの最小単位は何人なのか、というところからです。
例えば、私はセガと同じくらい、カプコンというゲームメーカーが好きなんですが、もともと自分自身がデザイナーでしたので、グラフィック面でデザイナーが強い力を持っているカプコンに憧れがありました。特にアニメーションの妙技、溜めと抜きのディフォルメがすごい。ゲームセンター向けの『ヴァンパイアハンター』の基板を買って、VHSで録画して、お酒を飲みながら各キャラクターのアニメーションを再生して見るのが好きだったんです。
――『ヴァンパイア』シリーズというと、西村キヌさんたちの仕事ですね。
松田 そうですそうです! キヌさんや、あきまんさん、BENGUS(別名:剛田チーズ)さんたちデザイナーさんのアニメーションが本当に最高で! この人達は天才だ! 素晴らしい!って……何の話でしたっけ?
――ゲームクリエイターの最小単位、という話です(笑)。
松田 そうでした(笑)。そのカプコンで、私は『ストライダー飛竜』というゲームが好きだったんですが、この作品はすごく少人数で創られたそうです。企画やディレクションの方がポスターまで描かれていて、ゲームを出すために必要なものがあれば、当事者たちが何でもやっていたんです。そういうのが、ゲーム作りの根本じゃないかと思うんですよ。
それで、ゲームを作るパッケージングに必要な最小人数は何人なのか、なんです。それで考えて定義した人数が、4人。いまのスマートフォンビジネスは、ゲームにちゃんとコミットできて才能もある人間なら、4人でちゃんとしたゲームができるはず、それを証明したいと思いました。
――ということは、トイディアの最初のふたり、プラスふたりですね。
松田 残りのふたりにも目星はついていましたが、経歴のある実力者ですから、他のゲーム会社での安定を捨ててでもトイディアに来てくれ、というのは、最初は止めました。信用できるということは親しくもありますから、彼らの人生を動かす以上、自分たちへの確信ができるまでは、呼ぶべきではありませんし。なので、ふたりで始めました。
――まずは最小以下からのスタートですね。
松田 当時はちょうどUnity Japanが設立されたばかりでしたが、私はアメリカのクリエイターからUnityの有効性や流行を聞いていたので、スマートフォンで作るなら日本的にツールから作るのでなく、そのパワーは全部クリエイティブに使うべきだと考えました。Unityなら、最悪アメリカから情報を入れればなんとかなるだろう、アセットストア(編注:Unity開発者向けに既成データを販売するオンラインストア)で仕入れることもできるだろうということで、個人輸入で導入して、まず最初にランゲームを作ってみたんです。それでトイディアのいまの表現力はこのくらいでいけるかな、というのが分かったところで、4人にすることにしました。
――トイディアの初期作になる『Moto Jumper』シリーズは、実験作でもあったわけですね。
松田 そうです。でも、実は最初は日本では配信しませんでした。セガやマイクロソフトにいた松田がなんか始めた、という妙な注目の浴び方もイヤだったので。といっても、アメリカで大ブレイクして、実績を出して日本に凱旋したらクールじゃん、という夢はあって、公開から3日間くらいソワソワしてたんですけど、箸にも棒にも引っかかりませんでした(笑)。
――気持ちは分かりますね(笑)。
松田 どうやらそういうものではないんだな、と分かって(笑)、身の程をわきまえて、ちゃんとゲームを作るようになりました。

(2015年4月収録)
前編はここまで。
後編は、ついに『ドラゴンファング』がなぜ100万ダウンロードを達成できたのか、その理由についてズバリ聞いた。ここでしか聞けない話、お楽しみに!
『ドラゴンファング ~竜者ドランと時の迷宮~』のダウンロードはコチラ